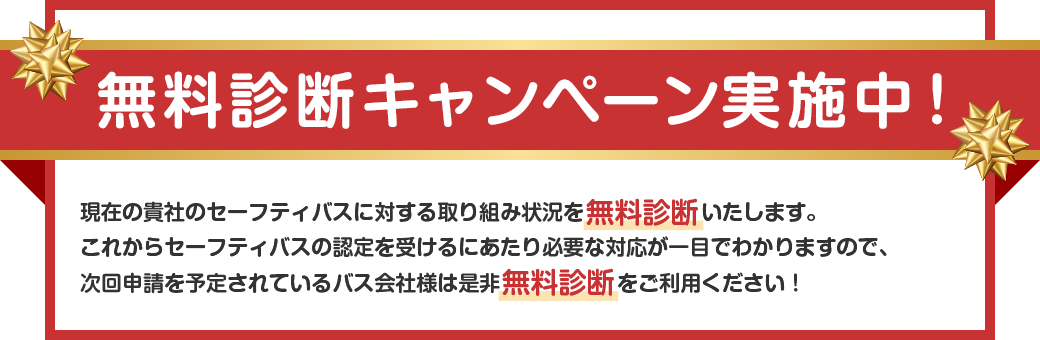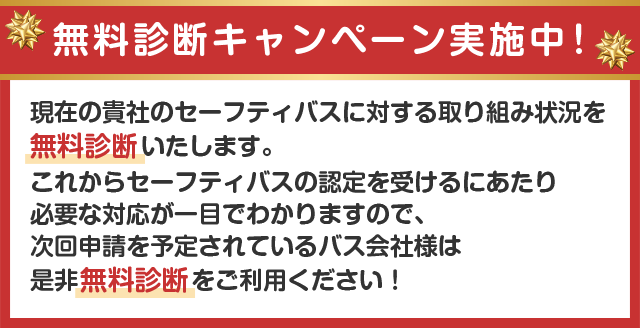徹底解説 セーフティバス
当文章は、
貸切バス安全性評価認定制度についてSBサポートが解説を加えたものであり、
貸切バス安全性評価認定制度の認定取得を保証するものではございません。
当情報は平成30年度のセーフティバス申請書を元に記載しております。
帳票類の整備・報告等
- 事故の記録
- 自動車事故報告書
- 乗務員台帳の記録内容
- 運転者ではなくなった者の乗務員台帳
- 車両台帳・車検証
ここでは事故報告フォーマットが必要事項を満たしているか、保管ができているかが問われます。
事故がないことが最も望ましいのですが、
万が一事故を起こしてしまった場合、所定のフォーマットに記載して保管する必要があります。
所定のフォーマットが正しく使えており、ファイルなどで大切に保管できてますか?
古いフォーマットで、必要事項を満たしてないケースも見受けられます。
乗務員台帳についても同様です。
保管に関しては、
セーフティバス申請書類の提出時に使うような分厚いファイルが望ましいと思います。
紛失を極力防ぐことができ、綺麗に保管できます。
薄い紙のファイルやクリアファイルはいけないことはありませんが、少々難があります。
運行管理等
- 運行管理規程
- 服務規程
- 運行管理者の選任
- 運行管理者講習
- 運転者の確保
- 勤務時間、乗務時間、交代運転者
- 点呼
- 乗務記録(日報)
- 運行記録計
- 運行指示書
- 乗降時の安全確保
- 営業区域
- 運送引受書
- 指導監督等
- 適性診断
- 特別指導
こちらも事故報告フォーマット同様に、最新のものが使われているかどうかが重要です。
「あるから大丈夫」とたかをくくらず、必ずチェック項目を確認してください。
古い場合は今すぐにバージョンアップしていただき、制定日を記載してください。
運行管理者に関しては、平成29年12月1日より、車両39両まででも2人必要となっております。
- 39両まで・・・2人
- 40両~59両・・・3人
- 60両~79両・・・4人
- 80両~99両・・・5人
- 100両~129両・・・6人
運行管理者の必要選任数を1名とする営業所の特例は、次の4点を満たす必要があります。
- 事業用自動車の数が4両以下
- 専ら回送車の輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
- 一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域に存する営業所
- 専ら車椅子での乗降装置および車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
選任された運行管理者には「2年ごとに1回」の受講が義務付けられています。
注意が必要なことは、「年度」の取り扱いです。
「1年」とは、「4月から翌年3月まで」というくくりになります。
例えば、平成28年2月に受講した方は平成27年度に受講したことになります。
間違えずに必要なタイミングで受講をしてください。
未受講であれば、下記URLを参考に早めの受講をお勧めいたします。
参考サイト:独立行政法人自動車事故対策機構
http://www.nasva.go.jp/fusegu/mng_kaijo.html
運転者の確保に関しては、苦労されているバス会社様も多いのではないでしょうか。
そもそも必要な運転者数とは? どうやったらうまく採用できるのか?
色々な悩みがあると思います。
適正な人数といってもそれぞれバス会社の考え方によりますので、
運転者の休息時間等を守れるだけの人数を揃えることが最低限になります。
できれば、それよりも1名・2名の余裕があればと思います。
採用の方法に関しては、
- 知り合い・出入り業者のスカウト
- ハローワークの求人票の書き方の工夫
これらのことが無料でできるでしょう。
採用事例としては、
バス会社様に出入りしていた旅行会社の社員さんで定年を迎えた方をスカウトし、
運転者として働いていたいただいているケースもありました。
- 昨年の従業員の総運転時間は○○時間だった
- 一人頭の総運転時間は△△時間だった
- 今後法令よりも運転時間の余裕を持たせるために、一人頭の総運転時間を□□時間にしたい
- そのため、今後××人の採用を計画している
- 採用施策は◎◎だ
このような計画であれば、ある程度論理的と言えるのではないでしょうか。
改善基準告示も今一度確認をお願いいたします。
参考サイト:厚生労働省 バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html
「改善基準告示よりも厳しい社内基準、その証拠」
これについてはそれを継続的に実施できているかがポイントになります。
そのため、一朝一夕で点が撮れるものではありません。
- 社内規則に自社基準を記載している
- 自社基準を社内に張り出している
- それが現実に実施されている
例えばこのようなことが求められます。
最繁忙期の記録の提出も求められるため、普段からの取り組みが重要です。
三つ星を狙うバス会社様には必須の取り組みと言えるでしょう。
初めてセーフティバスを申請するバス会社様には少々ハードルが高い内容かもしれません。
1年後にセーフティバスを申請するバス会社様は、
是非今からこの取り組みを初めて得点が取れるようにしていただきたいところです。
コメントの書き方に関しては、いかに論理的に書けるかどうかです。
誰が見ても納得できるような論理性が必要で、ツッコミどころが多くならないようにしてください。
アルコールチェッカーは、高ければ十数万円、安ければ数千円で販売されております。
ここは必要な投資だと考え、思い切って高性能アルコールチェッカーを購入しましょう。
それだけで3点獲得ですし、
飲酒運転撲滅を実現できるので投資対効果は十分にあると考えてください。
デジタコ・ドラレコも同様です。事故を防げて教育にも使えると考えれば、必要な投資です。
ドラレコは一般乗用車でも普及がかなり進んでますし、
プロドライバーがつけない理由もなく、義務です。
参考サイト:貸切バスに対するドライブレコーダー義務付けについて
http://www.jaspa-saga.or.jp/html/member/17_04/17_0403.pdf
点呼・日報・運行記録計・運行指示書・運送引受書に関しては、掲載必須項目があります。
最新フォーマットを使用できているか、今一度確認をお願いいたします。
指導監督等は、年間教育計画が作成できているかが重要です。
必ず計画的に教育を実施していただきたいところです。
救急救命講習は、消防署に依頼をすると実施していただけます。
急な依頼は嫌がられますので、これも予め余裕を持って依頼することをお勧めいたします。
ドライブレコーダーを活用した教育は、
セーフティバス申請の中では四半期に一度以上の頻度で教育をしていることが求められています。
しかし、せっかく設備投資をしたものを四半期に1度しか実用化しないのは非常に勿体無い話です。
これは各バス会社様に提案しておりまして、
毎月の会議の際に定期的に実施することをお勧めしております。
このパートだけでなく他のパートにも関係するポイントとして、
毎月の会議を実施する際にアジェンダを作成して、
セーフティバス認定に必要な項目を毎月確認していけば、
セーフティバス認定取得もさることながら更新にも十分対応できるんだと思います。
案外それができているバス会社様は少ないのではないでしょうか?
安心・安全への取り組みは日々のコツコツした積み重ねが何よりも重要です。
毎月の会議で、是非全社員でその取り組みをお願いしたいところです。
議事録も必須ですね。苦手な方が多いのでしょうか。
- メインコンテンツ