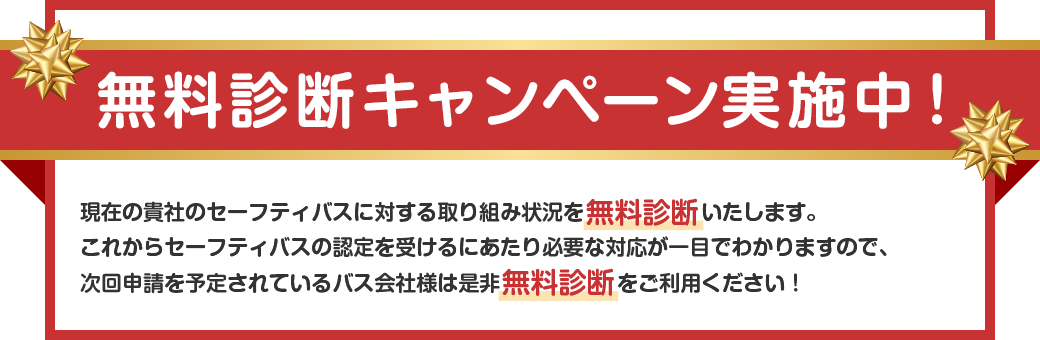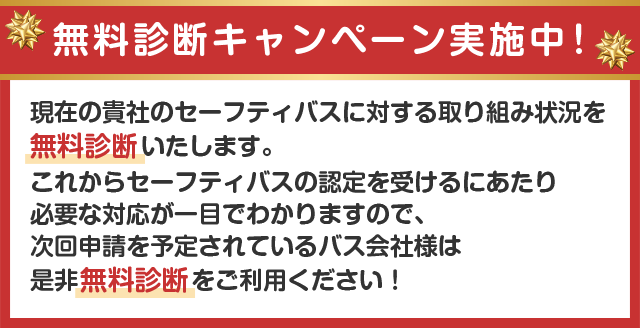徹底解説 セーフティバス
当文章は、
貸切バス安全性評価認定制度についてSBサポートが解説を加えたものであり、
貸切バス安全性評価認定制度の認定取得を保証するものではございません。
当情報は平成30年度のセーフティバス申請書を元に記載しております。
その他
次のどちらか1つをいたしておれば、上位項目として配点があります。
- 自社独自の無事故期間が記載されている運転者表彰制度を示す社内文書や社内規定の写し等
- 過去2年間に警察署などの外部機関から安全に関する事項で表彰された実績を示す資料
事故がなければ話が早いですね。
無事故を継続して、セーフティバスでも高得点を狙ってください。
自社独自の運転者表彰制度、例えば3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月無事故が続けば、
社内会議で表彰され社内に賞状が掲示される。
寸志が貰えるなど、何か無事故運転者に対して報いる制度を作ってください。
その結果を社内に掲示しているとわかりやすいですね。
就業規則などに制度の内容を盛り込んでおくのも良いと思います。
無事故を称える文化が社内に根付いていれば美しいですね。
人は褒められれば、それが快感になりまた褒められたいと思うものです。
その連鎖が無事故継続の秘訣のひとつかもしれません。
独自でその文化を築けていれば美しい会社だと思いますし、そのような会社でありたいものです。
ここからは会社の規模により少々基準が変わってきます。
多くのバス会社様は中小規模事業者に該当します。
- 車両が200両以上あれば、大規模事業者
- 営業所が2箇所以上、車両200両未満であれば、準大規模事業者
- 営業所が1箇所、車両が100両未満であれば、中小規模事業者
そもそも運輸安全マネジメントは、何をしなければならず、何を目的としているのか。
今一度その意義を確認してください。
参考サイト:国土交通省 運輸安全マネジメント制度の理解を深めるために
http://www.mlit.go.jp/common/000045759.pdf
ガイドラインも出ております。
文字ばかりで分かりづらいかもしれませんが、
やるべきことを明確に書いていただいているので、大変参考になります。
まだ運輸安全マネジメントに取り組んでいないバス会社様は、
このガイドラインを元に方針を作成すると分かりやすいと思います。
参考サイト:国土交通省大臣官房 運輸安全監理官
運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
~輸送の安全性の更なる向上に向けて~
http://www.mlit.go.jp/common/000110883.pdf
計画その1
運輸安全マネジメントに取り組むために輸送の安全の確保について責任ある体制を構築しているか。
次の3点を満たせば2点獲得です。
- 経営者は、法令遵守、安全最優先を基本とした安全方針(安全に関する基本方針)を作成している。
- 組織体制及び指揮命令系統の組織図の作成等必要な措置が講じられているか。
また、安全統括責任者(管理者)は、運行管理整備管理が適正に行われているよう両管理者を統括管理し、安全の確保に関する事務の統括管理を行っているか。 - 「安全統括管理者の選任及び届出」と「安全管理規程の作成及び届出」を行っているか。
運輸安全マネジメントの取り組みで、初めに出てくるのが安全方針の作成になります。
安全方針には、少なくとも次の事項を趣旨を盛り込む必要があります。
- 安全法令等の遵守
- 安全最優先の原則
- 安全管理体制の継続的改善等の実施
これは会社の基本理念に近しい内容です。社長の安全に対する考え方を明確に示してください。
そして、作成されている安全方針は従業員に内容を理解させ、実践を促す必要があります。
会議や朝礼などで周知徹底を図ることが必要です。
その安全方針を、社内に掲示しておくと分かりやすいでしょう。
少し手を加えるとすると、社員が携帯できるような小さなカードに印刷するのも一つです。
いわゆる「クレド」というものです。
財布や名刺入れ、ポケットにも収まるサイズのカードですね。
いつでも自社の安全方針を確認できるようにしておけば、周知徹底も容易ではないでしょうか。
コメントに関しては一言だけにせず、文章を記載してください。
ここのコメントが薄ければ、普段から安全に対する取り組みも薄いと感じてしまいます。
ガイドラインなどで求められているレベルは明らかなので、
それを少し上回る自社の工夫を考えてみてください。
その少し一歩先ができていれば、コメントを記載することは容易ではないでしょうか。
ヒントは他社の事例を参考にするか、社長の自論を展開することです。
答えはありませんので、自社なりの取り組みを検討ください。
- メインコンテンツ