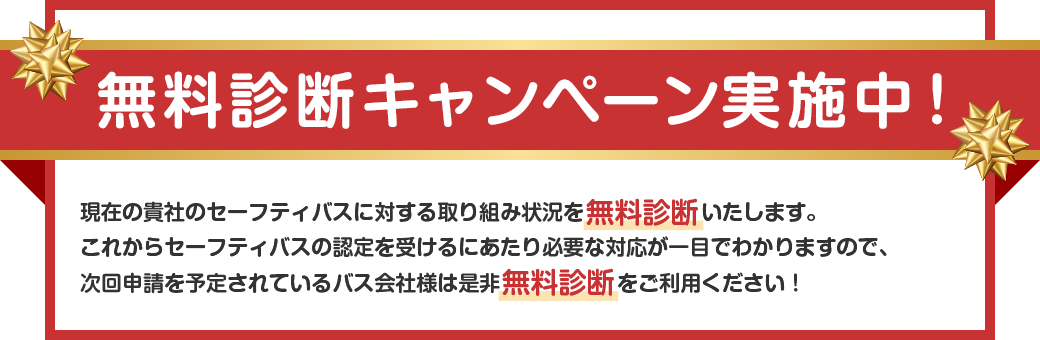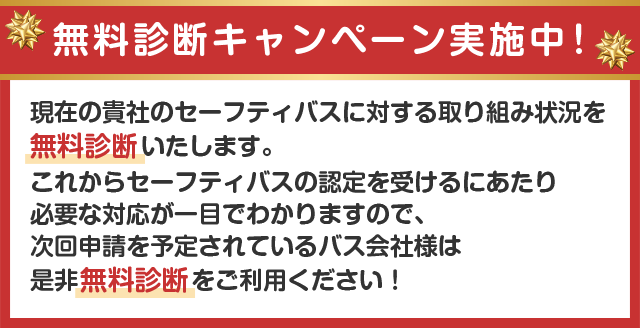徹底解説 セーフティバス
当文章は、
貸切バス安全性評価認定制度についてSBサポートが解説を加えたものであり、
貸切バス安全性評価認定制度の認定取得を保証するものではございません。
当情報は平成30年度のセーフティバス申請書を元に記載しております。
車両管理等
- 整備管理規程
- 整備管理者の選任
- 整備管理者研修
- 日常点検
- 定期点検
整備管理者に関しては、
ルールを守っていただき必要な研修の受講をしていただくようにお願いします。
研修の日程は都道府県によりバラバラだと思いますので、
早めにスケジュールを立てていただくようにしてください。
日常点検もチェック項目が決まってます。
上位項目として、決められた項目以外に1つ以上自主的に追加をする必要があります。
シートベルトの確認・バックカメラの確認・非常口の確認・窓の亀裂の確認など、
考えれば色々な項目が候補に挙がってきますね。
定期点検に関しては、過去1年間の3ヶ月点検の定期点検整備記録簿の写し
(計4枚、内1枚は車検時の12ヶ月点検表)を営業所毎に添付する必要があります。
上位項目としては、頻度が問われます。3ヶ月よりも頻度をあげた点検をする必要があります。
2ヶ月点検・1ヶ月点検・45日点検など、自主的に車両の安全を確認してください。
こちらも日頃からの取り組みが重要になります。
少しの工夫で十分得点できる項目になりますので、
認定を維持しようとお考えのバス会社様は是非とも頻繁に点検をお願いいたします。
労基法等
- 就業規則
- 36協定
- 労働時間
- 健康診断
就業規則の全文と、従業員代表又は労働組合の意見書の添付が必要です。
意見書は例え批判的なことを書かれたとしても(あまりそのようなケースは見受けられませんが)、あくまでも意見であり必ず対応しなければならないというものではありません。
従業員が10名未満の場合、就業規則の労基署への届出義務はありませんが、
インターネットの発達により労働基準法に少し詳しい従業員も増えており、
会社が訴えられるケースが増えております。
会社を守るという観点で、どの事業所も就業規則の作成は必要な時代です。
稀に36協定を結んでいないにも関わらず残業をしていたり、
毎年更新していなかったりと不備があります。36協定を結んでいれば、毎年提出をしてください。
労働時間の上位項目として、1年に1回以上の頻度で2年以上、
全従業員に労基法・改善基準告示の教育を行った証明が必要になります。
これは定例会議で実施し、従業員にレポートを書いていただくか理解度テストを実施するなど、
何か書面での証拠が望ましいでしょう。
労基法は度々変更になりますので、毎年必ず時期を決めて実施することをお勧めいたします。
これもセーフティバスの認定を継続させるためのポイントになりますね。
健康診断の上位項目も、事前の取り組みが必要になります。
次の2点を満たす必要があります
- 全運転者の3割以上の運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査を実施していることを証する書類の提出
- 運転者に対して、健康診断実施時に年齢に応じて生活習慣病(成人病)検診や脳検診等を1名以上に実施していることを証する書類
- 運転者の健康状態や疲労状況の把握等に効果が高い、携帯型心電計、居眠り警報装置等の機器を1台以上導入していることを証する書面(請求書や領収書等)
全て投資が必要なものです。安全への投資は惜しまずに。
特に③は、いわゆるウェアラブル端末ですね。
まだまだ導入しているバス会社様は少ないように思いますが、
これからの時代どんどん導入する企業が増えることでしょう。
バス事故の原因の中で、疲労・居眠りは非常に多いです。
それを事前に察知して重大事故を防げると思えば、高くない投資だと言えます。
- メインコンテンツ