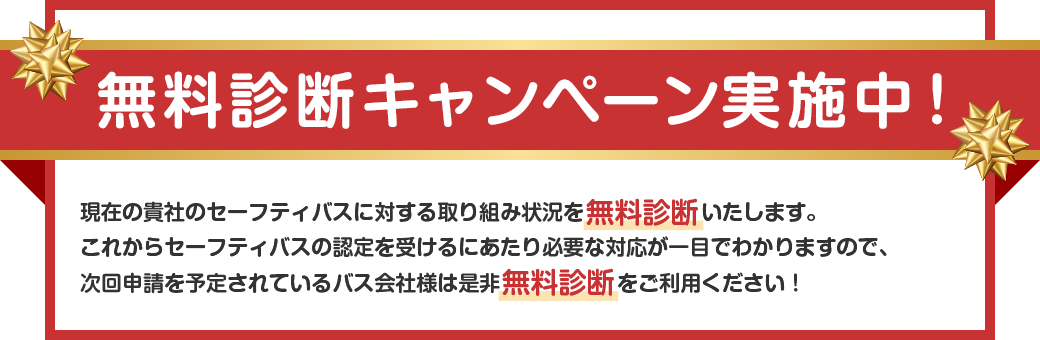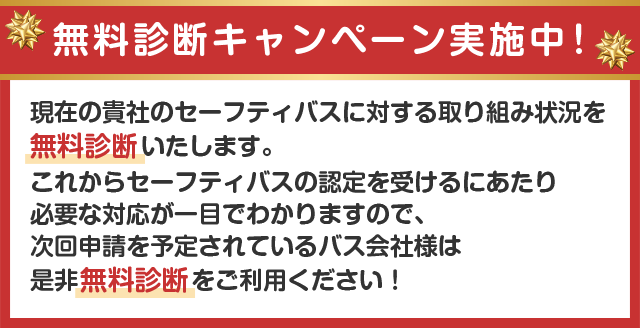徹底解説 セーフティバス
当文章は、
貸切バス安全性評価認定制度についてSBサポートが解説を加えたものであり、
貸切バス安全性評価認定制度の認定取得を保証するものではございません。
当情報は平成30年度のセーフティバス申請書を元に記載しております。
計画その2
ここは事業規模により内容が異なります。
- 経営者は、安全方針(輸送の安全に関する基本的な方針)を社内に周知しているか
- 経営者は、関連法令の遵守と輸送の安全確保が最も重要であるという意識を社内に周知しているか
※2項目目は大規模・準大規模事業者のみ
こちらも毎回会議の度に、この項目の確認や唱和を行っておけば問題ないでしょう。
会議のアジェンダに当内容を盛り込み、議事録で周知してた証拠を残しましょう。
何事も一朝一夕にはできませんので、普段からの地道な取り組みが功を奏します。
計画その3
- 経営者は、安全方針を実現するための安全目標を1年毎に作成しているか。
- グループ企業にあっては、参加の企業が密接に協力し一丸となって安全性の向上に努めているか。(グループ企業がある事業者のみ)
- 輸送の安全に関する投資額の具体的な目標を設定しているか
中小規模は初めの1項目のみで2点、その他規模は全部で2点です、
ここの1項目は、毎年安全目標の作成を求められています。
「2018年度安全目標」
という具合に、毎年毎年新しい目標の設定をして、社内に掲示していただくことをお勧めします。
ヒントとしては、国土交通省がメールマガジンを発行していて、全国の事故情報を共有してます。
そこに出てくる情報見て、
最近多い事故や問題となっている事柄を参考にしながら目標を立てることです。
他山の石として、自社がより安全の徹底ができるようにしてください。
準大規模・大規模企業でグループ会社がある場合は、
顔を合わせた定期的な会議を実施することをお勧めします。
地域の情報共有ができる貴重な場でもありますし、
同じ仕事をする仲間として定期的に顔を合わせ議論することが、
安全意識の向上につながることは間違いないでしょう。
投資に関して言えばデジタコ・ドラレコの設置は当然として、
車両の購入計画・ウェアラブル端末の導入・高性能アルコールチェッカーの購入など、
新しい設備により事故を減らすことを検討してください。
最近では衝突被害軽減ブレーキなども登場し、
最新設備には安全対策がかなり備わってきております。
どうしても事故原因は人的要因が多く、ヒューマンエラーの撲滅はゼロにはできません。
そこを設備がカバーしてくれるのであれば、導入しない手立てはないでしょう。
すぐに全ての設備を更新することは難しいので、3年・5年先の計画を立ててみてください。
計画その4
- 経営者は、安全目標を達成するための安全計画を作成しているか
「安全目標」という言葉が何を指しているのか。
色々な捉え方ができますね。
サンプルで記載しているように、
年間の安全教育実施計画があればここの項目はクリアできるのですが、
是非それ以上を目指していただきたいところです。
実施その1
- 運転者に対して、安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施し記録しているか
- 経営者は安全にかかわる者には、外部機関が主催する輸送の安全に関する研修会・講習会等を受講させているか。
- 評価基準10を満たし、国土交通省の認定セミナーを受講した場合は2点
- 評価基準10を満たし、国土交通省以外の研修会・講習会東野受講は1点 - 運転者の安全に資する技能等の向上に努めているか
- 運転者に対する教育及び研修については。次の①及び②の内容を実施しているか
①運転者等の年齢、経歴、能力に応じたもの
②知識普及、問題解決、参加体験型(一方的な講義ではない方式)
運転者に対して、計画的な研修が実施できてますか?
ここではただ単に年間教育を作って実施しているだけでは、
求められている基準を満たしているとは言えません。
「写真など、研修の証拠を残しているから大丈夫」
そういう問題でもありません。
必要なことは、計画性と研修の質です。
セーフティバス申請において、
前段は法令遵守ができているかどうか、最低限ルールを守れているかの確認です。
最後の運輸安全マネジメントは、その上を求められています。
一つ星を取るためには、次のような基本的な事柄が対応できていれば問題なく取得できます。
- 法令遵守
- 無事故無違反
- 最低限の講習への参加
ただ、三ツ星をとってキープするには、
運輸安全マネジメントを作成し、継続させなければなりません。
中々ハードルが高いですよ。
記録に残すにしても写真を取るだけではなく、文章の質も大切です。
「○月○日 実習▲を実施」
これだけではダメですね。
○月○日○時~○時
研修内容:
研修実施者:
参加者:
研修の目的:
研修の成果:
反省点:
普段の業務へどのように役立てるか:
これぐらい詳細なレポートが必要になります。
いつ、誰が、何をして、どのように感じて、仕事にどのように役立つのか、
誰がみても、これらの項目がわかるようにしておいてください。
そのような視点で各研修を計画的に実施して行くと、
安心・安全なバス会社になることは間違いないでしょう。
結果、お客様に喜んでいただけ、仕事のリピートがくるようになるでしょう。
年間の研修計画は、期首に立ててください。
外部の研修、例えば一般講習や防災訓練など日程が決まっているものがありますので、
期首に全て予定を立て、申し込みまで済ませてください。
「ついうっかり受講を忘れていた!」
そのようなことではいけません。
- メインコンテンツ